少し時期外れではありますが、今年も我が家の庭のヒガンバナが綺麗に咲きました。
写真をやっていると色んな花を撮りますが、サクラ、ヒマワリ、コスモスなどの定番の被写体に加えてこのヒガンバナももう定番と言っても良いと思うのです。
と、言うのも、自分がまだ小学生頃とかはサクラやヒマワリ程被写体としてメジャーではなかったと記憶しています。勿論その頃には既にヒガンバナが咲き乱れるような景勝地のようなスポットはあったのでしょうが、特に街や都会ではもう身近な花とは言えない存在だったでしょう。
コンテンツが溢れる現代、SNSでは紅く鮮やかに群生するヒガンバナの素晴らしい風景写真の他、和製ホラーゲームでは特にその存在感が際立っています。ここまでヒガンバナが市民権を得たのは割と最近の話なのでは?と、感じるのです。
目次
- ◆彼の岸に咲く紅い花
- 露纏う朝
- 柔らかい風の昼下がり
- 霧雨の夕暮れ
- ◆彼岸花とは何か
- 葉見ず花見ず
- 名前の由来や分布、有毒性
- ◆淡い泡沫の夢
◆彼の岸に咲く紅い花

どこかの景勝地とかではありません。単純に自分の家の庭です。なので、少数株が庭や畑や墓の傍にチラホラ咲いているだけです。
この花が咲く頃我が家では、丁度稲刈り作業が終わり頃を迎えています。稲刈りはとにかく忙しいので、気付くといつの間にか咲いていた…って感じで花を見つけます。
●露纏う朝

9月も終わりを迎えるこの頃、朝晩の気温差が広がり始めて草木が朝露を纏うようになる。特に朝から陽が射すような日には時折、雨でも降ったのかと思わせるくらい沢山の水滴を纏う。
煌めく朝露の光の中を覗こうとすると、向こうには逆さになった別の世界が広がっている。これは彼の花、そこに見えるのは彼の岸か。
●柔らかい風の昼下がり

すっかり夏が過ぎ去って、日ごと寂しさを増していくようにも見えるけど、時折思い出したかのように夏の陽気に包まれて、忘れかけていく少年の頃を思い出す。
温かい日差しに包まれて、収穫期の心地よい疲れを高く広がる秋の空に開放していく。吹き続ける風の音が耳元で今年の夏の出来事を語ってくれるようで、なんと言うか…こんな時間がずっと続けばいいのになと思う。
●霧雨の夕暮れ

今年の米の出荷が全て終わった。籾摺り作業をしていた納屋の中は、機械も片付いてガランとしている。霧雨が舞う静かな朝。
庭の彼岸花は満開で見頃を迎えていた。蕾だったものも全部咲いた。彼岸の頃に咲くからそう呼ばれるようになったと言われているけど、きっと咲いている間だけあの世とこの世が通っているのかも知れない。
PR
–
MUJIBOOKS(無印良品)推奨のフォトブック『BON』- あなたが丁寧に撮った花の写真を作品集に◆彼岸花とは何か
改めて見てみると実に不思議な花です。花弁の形や咲き方、葉っぱが無い所など見れば見る程不思議な花です。

●葉見ず花見ず
彼岸花は『葉見ず花見ず』と呼ばれ、他の植物と違って花と葉が別々に開きます。最初に球根から緑色の茎がスラっと伸びてきます。ある程度伸びると緑色のスラっとした茎に付くには少々違和感を覚えるような鮮やかな紅の蕾が付きます。花が満開になって一周間程で枯れて散ってしまうのですが、その後に細長い葉がフサフサと出てくるのです。花は葉を知らないし、葉は花を知らない…珍しい性質の植物です。
●名前の由来や分布、有毒性
そんな不思議な彼岸花、一体どういう植物なのか改めて調べてみました。
彼岸花は別名『曼殊沙華』と呼ばれますが、自分はヒガンバナという呼び名が通称で曼殊沙華が本名だと思っていました。どうやら仏教にまつわる呼び名のようです。法華経の仏典ではお釈迦様が法華経を説かれた際、これを祝して降った花の一つがこの彼岸花だったそうです。
学名ではリコリスと呼ばれ、ギリシャ神話のリュコーリアスという神様にちなんでいるようです。(以上ウィキペディア)
彼岸の頃に咲く
彼岸とは春分の日と秋分の日を中日にして一週間が期間になっています。彼岸花はこの内秋彼岸の頃によく咲きます。勿論それ以外のタイミングでも咲きますし、平野部や山間部で階下の時期が異なる事もあります。
調べてみると秋分の日は国民の祝日に関する法律によって、『先祖を敬い亡くなった人を偲ぶ祝日』とされています。因みに春分の日は『自然を称え生物を慈しむ日』とされています。
日本では帰化植物
彼岸花の原産国は中国大陸です。元々日本にこの花は咲いていませんでした。渡来起源は諸説言われていますが、有史以前の事で詳しい事は分からないそうです。
有力な説は稲作と共に日本へやってきたと言う説です。これは昔から結構聞きました。稲作は現在の中国から縄文時代の日本にやってきたものなので、原産国が中国ならほぼそれで間違いないのではと思います。
たまに変な所で咲いている彼岸花を見かけますが、基本的に人の手が入っていない所では咲きませんのでかつてそこは誰かの庭か畑だったのでしょう。そんな感じで各地で野生化している彼岸花は結構あると思います。
余談ですが、狩猟の下見の為にとてつもない山奥に入った時の事、初めて入ったエリアで沢登りや藪屋などの物好きでも入らないような所を探索した時に妙に開けた所を発見しました。たまに山抜け(地滑りなど)でそんな地形になる事がありますが、結構平坦だったんでなんだろうと思ったら森の切れ目に彼岸花が咲いていました。
それらしい遺構は見つけなかったのですが、かつてここには人が暮らしていたという事でしょう。仏教に由来する事が多いこの花があると言う事は、それなりの間そこには人の暮らしがあったと思います。廃村になったのか、はたまた里へ降りたのか。
死に至る猛毒の花
さてそんな彼岸花、有毒植物としても有名であります。非常に毒性の強いアルカロイドが含まれていて、含有差はあるようですが全草有毒です。因みに毒成分の中にリコリンというのが含まれているのですが、学名のリコリスから付いたものだそうです。
同じアルカロイドを含む有名な有毒植物にトリカブトがあります。下痢や嘔吐の他、中枢神経に作用し最悪死に至る毒です。
彼岸花はその毒性を活かしてモグラ対策の為に田んぼの畔に植えられている事があります。今ではすっかり景観の為ですが。仏教的な意味も含め多分同じような理由でお墓の周りにも植えられたと思います。
トリカブトも毒矢などの武器的な利用方法が有名ですが、詳しい処理の方法は分かりませんが彼岸花もトリカブトも漢方で薬として利用できるそうです。
◆淡い泡沫の夢

彼岸花。彼の岸には先立った大切な存在が居る。家族や友人はもちろん、『小さな家族たち』も。
彼の岸は、この世の苦しみが無いところ。この世はとにかく苦しみばかり。悲しい事ばかり。どんなにつつましく暮らそうとしても、人は人を構わずにいる事ができない。そこに生涯終わりのない苦しみが生まれる。
この花が咲いている間だけ、先に向こうへ行った者たちに会えている気がする。
この花が咲いている間だけ、先に向こうへ行った者たちと言葉を交わしている気がする。

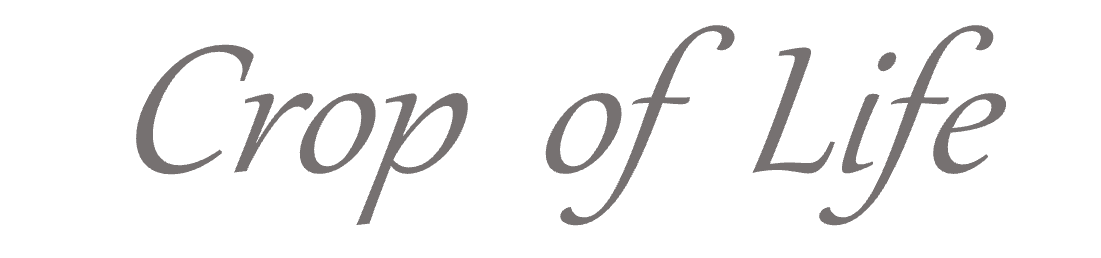




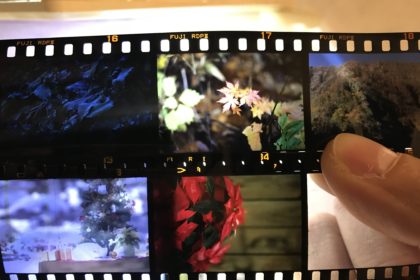
コメントを残す